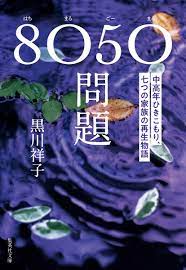今年も残すところあと二週間、一年間で読んだ本や観た映画はそう多くないが、やはり好みが集中していたように思う。それは閉鎖的な人間関係、とりわけ家族に濃密な一年であったためだろうか、どうしても家族をテーマにした作品が印象深い。
小説に限らずノンフィクションでも先日手に取ったのは『8050問題 中高年ひきこもり、七つの家族の再生物語』(黒川祥子 集英社2021)だった。ひきこもりは家族のあり方と関係が深いと筆者は繰り返し述べ、それも家族ごとに千差万別であるとする。私自身50歳代となり様々な支えによって生かされている一方、社会的ひきこもりとも言える状況に自分の問題として興味深く読んだ。そしていくつかのケースのどれにも当てはまることは無かったが、せめて息子との関係をこうはしたくないと思った。家族の問題、とは言ってもいずれのケースにも母親が重要なファクターとして存在しており、虐待や支配、ネグレクト、過保護、過依存などなど親として機能していなかったことに起因する。父親がしっかりしていれば防げたかもしれないが、そこに夫婦の不仲があり精神的な弱さや病、あるいは先天的な障害なども加われば夫婦の絆など脆い。
そもそも問題という日本語の意味は広い。例えば英語のproblemを辞書で調べると類義語としてproblem, matter, question, issue などが挙がっている。これによれば8050問題などは社会や組織全体に関わる、解決されるべき「問題」であるからproblemがふさわしい。こうした状態は良いところが一つもないから、親子共倒れにならないよう各々自立することを最終目標とする。
主に小説や映画で取り上げられるのは、明確に答えがわかっているquestionではなく、個人的に決断を迫られているmatterでもなく、議論を必要とするissueに近いのかもしれない。それよりもっとグレーな、解決なんかできないようなモヤモヤしたものが「家族の問題」における問題なんだろうと思う。少なくとも今年私が目にした作品はどれも、全否定も部分否定もなく全肯定せざるを得ないような結末だった。
映画では是枝裕和監督の作品をいくつも観た。『万引き家族』『三度目の殺人』『空気人形』『海街diary』など。社会的にはアウトでもそういうのもアリじゃないか、全否定できないだろう?みたいな、単に「優しい」では括れない何とも不健全なリアリティが伝わってきた。だからつい家族の問題には答えがないのだろうと思ってしまう。